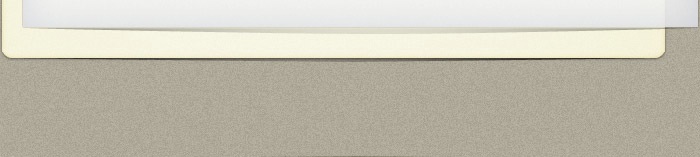木曽檜は、青森のヒバ、秋田の杉と並んで日本三大美林と呼ばれています。
木曽檜に目が向けられたのは室町時代に入ってからであり、本格的な開発は豊臣秀吉に始まると言われます。
江戸時代には尾張藩の直轄領となり、さまざまな保護と規制が行われました。
一切の立ち入りを禁止する「留山(とめやま)」、そして檜、サワラ、アスナロ、コウヤマキ、ネズコのいわゆる木曽五木の伐採が統制され、資源保護が行われたのです。
また、伊勢神宮の「式年遷宮」の用材として使われるなど、木曽檜は歴史とともに歩んできました。
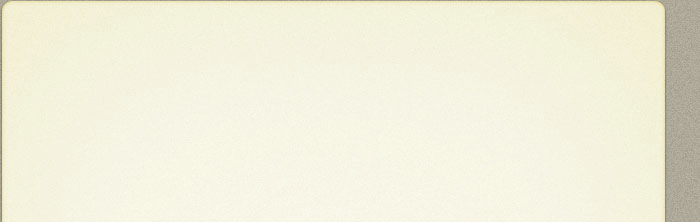

木曽檜は、青森のヒバ、秋田の杉と並んで日本三大美林と呼ばれています。
木曽檜に目が向けられたのは室町時代に入ってからであり、本格的な開発は豊臣秀吉に始まると言われます。
江戸時代には尾張藩の直轄領となり、さまざまな保護と規制が行われました。
一切の立ち入りを禁止する「留山(とめやま)」、そして檜、サワラ、アスナロ、コウヤマキ、ネズコのいわゆる木曽五木の伐採が統制され、資源保護が行われたのです。
また、伊勢神宮の「式年遷宮」の用材として使われるなど、木曽檜は歴史とともに歩んできました。
歴史とともに歩んだ木曽檜

健康にも良い天然の良材
木曽檜は厳しい自然環境の中で50年、100年という長い歳月をかけてゆっくりと成長するため、1cm幅に10年以上の年輪が詰まった、きめが細かく緻密で見事な材となります。細かい年輪が美しく、良い香りがして加工も容易で狂いも少ない、世界的にも優れた建築材です。
また、強い殺菌効果や炎症を鎮める消炎作用を持つ薬用成分ヒノキチオール、樹木や植物が自らの身を守るために放出する森の芳香フィトンチッドなどを通して、私たちの心と体に多くの健康効果をもたらしてくれます。
循環型の森林資源利用をめざす
木曽檜は、先人達のたゆみない手入れと植林によって守られ、今日まで美林を維持してきました。私達はその恵まれた立地の中で「木は伐るだけでなく、再び植えて返す」をモットーに造林にも力を入れています。山は手を入れなければ、すぐに荒れてしまいます。伐採した後には苗木を植え、間伐をして成長を促し、豊かな木曽檜の森を次の世代に引き継いでいくことが私たちの使命と考えています。
また、山からの贈り物である木を大切に使うため、気取りの無駄が出ないコンピューター制御による製材を行い、樹皮は全て牧畜用の敷き藁代わりに使って、出来た堆肥は大地に返すなど、循環型の木材利用を進めています。



木曽檜