新伝統構法
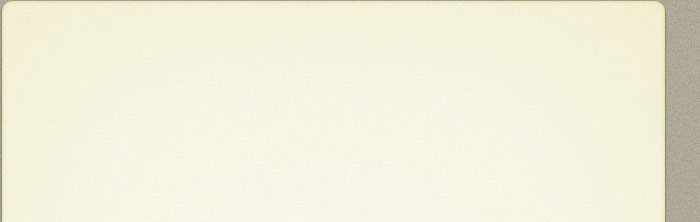

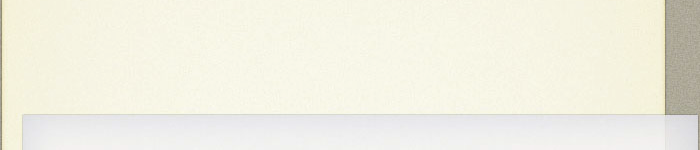
はじめに
現代の木造建築の大半が在来構法です。
本来日本の建築文化である、伝統構法が今日姿を消しつつあります。
その原因の一つに、建築金物の普及が在ると思われます。この金物に頼りすぎてしまい、木造建築本来の木組みの技術が影をひそめてしまったのです。
今日住宅金融公庫の仕様書を見ても、たしかに金物の使用は明記されておりますが、これは義務ではありません。これに変わるものとして、ダホ・こみ栓などの仕様も、記されております。
又、羽子板ボルトが金物の中でも一番数多く使われます。
これは仕口を蟻落としにするためで、これを渡りアゴにする事で羽子板ボルトの使用はなくなります。
新伝統構法は、日本の建築文化の主流であった 貫構法 をベースに現代のニーズに合わせて改良を加え、一般の木造住宅に普及できるようになりました。
しかし 現代の建築様式の中では、在来工法の普及により 継ぎ手・仕口が簡素化され、金物にたよりすぎています。新伝統構法の普及のためには、職人の木造建築に対する気構えが重要です。
新伝統構法の紹介
在来構法は土台・柱・桁(梁)に筋交いが入ります。
新伝統構法は土台・柱・桁(梁)に足固め・桁固め・通し貫きが入ります。
木材は常に収縮を繰り返します。
木材が乾燥する事により、金物の本来の強度はなくなります。現代の在来構法は金物に頼り、継ぎ手・仕口などが簡素化されており、金物強度がなくなった時に、建物は非常に危険な状態になります。
人工林桧は安い
これまでの伝統構法では、差し鴨居・桁・梁などに大きな木材が使われて来ましたが、現代の木造建築のニーズに合わせると、材の調達・乾燥・価格の点を考えても木材の準備に時間かかり、とても困難です。その策として、人工林の4寸角をベースに、重ね梁にする事で材の寸法を統一化しています。(常に一呈の寸法での乾燥が可能となる)
又、重ね梁にする事で、材のねじれなどが軽減されます。
梁を格子梁の形状にして、上端に天井材を貼ることで水平耐力壁を創ります。
間伐材のすすめ
人工林桧は、間伐しないと育ちません。
15年~20年で保育間伐をし、約20年周期で間伐をします。60年~70年で利用間伐をします。この時に全体の約3割が間伐材として切り出されます。
人工林桧を使う建物は、それに見合う量の間伐材を建築材として使わなければ山が維持できません。
この建物では、根太・垂木に間伐材を使用しています。
強度は、芯持ち材なので、十分ありますが、ネジレなどがでやすく、扱いにくいものです。このために、自然乾燥で桟を入れて3ヶ月間乾燥します。
取り付けた後は、ほとんどくるいません。
ダホの効果
小さな木材を重ねて合成梁とするときに、この材を一体化するために、ダホを使います。ダホは貫・幕板の厚みにあわせて、18ミリ~24ミリとします。
ダホ間隔は303ミリで・ズレ防止のために、竹釘をさします。


写真1 「重ね梁の交差部分」
ダホの位置に竹釘を打つ
写真2 「重ね梁と格子梁上木が
渡りあごで架かる」
人工林檜の120ミリ×120ミリを重ね、間に60ミリ×45ミリの幕板が入ります。
24ミリ×24ミリのダホが303ミリ間隔で入ります。


写真3
「重ね梁の下木が入ったところ」
写真4
「重ね梁の下木が入ったところ」
こみ栓の効果
ほぞ・継ぎ手の抜け防止にこみ栓を打ちこみます。ダホはズレに抵抗するのに対して、こみ栓は引きぬけに抵抗します。
材のネバリ・食い込みにより、力を吸収します。
土台・梁に幕板をダホ差し、柱を土台・梁にホゾ差し、込み栓(24ミリ×24ミリ)打ちとします。
足固め・桁固め
伝統構法では、框・差し鴨居などで、足固め・桁固めにしていますが、新伝統構法では土台・幕板・通し貫 若しくは土台・幕板・根太・大引き・框を足固め部材とし、通し貫・幕板・桁で桁固めとしています。
壁面の剛性は、通し貫で取り、筋交いは使いません。通し貫と柱に渡りあごをつけることで、桁にかかる水平荷重を、柱・貫を通して土台まで均等に伝えます。
割りクサビで貫を固定します。クサビも木材の乾燥により、緩びが生じますが、クサビの形状を考え、緩びにくくしています。
足固め
構造根太を雇いシャチ継ぎで取り付けます。




写真5
「重ね梁の下木が入ったところ」
写真6
「大引きの受け」
写真7
「幕板の打込み1」
写真8
「幕板の打込み2」

写真9
「幕板の打込み3」
桁固め 梁・幕板・通し貫での桁固
写真は開口部の吊束部分
金輪尻はさみ継ぎ格子梁の継ぎ手


写真10
「金輪尻はさみ継ぎの分解写真」
写真11
「金輪尻はさみ継ぎの組立例」
梁を渡りアゴで組み、渡りはX方向・Y方向90ミリの段差をつけます。
仕口部分のほとんどが渡りアゴになります。
屋根面は梁を使わずに、格子梁で組みます。




写真12
「格子桁の組立1」
写真13
「格子桁の組立2」
写真14
「格子桁の組立3」
写真15
「格子桁の組立4」
格子梁へ化粧野地(杉板)を張ります。
105角の格子の下に、105×60の材を付けてダホ打ちにします。


写真16
「通し貫の施工1」
写真17
「通し貫の施工2」
柱に通し貫が入り、120ミリ×120ミリの柱に30ミリ×120ミリの貫が貫通し渡りアゴを付けて割りクサビで締めて柱を拘束します。
貫の端部は蟻にしてクサビで締めます。
貫を通す作業は柱立てと同時に行い、入れ残しのないようにします。




写真18
「金輪継ぎの加工1」
写真19
「金輪継ぎの加工2」
写真20
「継ぎ手の仮組み1」
写真21
「継ぎ手の仮組み2」
継ぎ手は工場で仮組をします。
材の目違いを取り、長さ・曲がりなどの調整をします。


写真22
「継ぎ手の仮組み3」
写真23
「継ぎ手の仮組み4」


写真24
「作業の終わった部材」
この建物は、構造材の全てが120ミリ角で重ね梁と格子梁の組み合わせにより、大梁
を使わない構造になっています。
又、屋根も格子梁を組むことで大梁の無い空間ができます。
しかし、大梁の架構に比べかなりの手間と時間がかかるために、大梁のタイプが主流となってしまうのが現状なのですが、梁材は同径材で計画し事前に乾燥させることで効率よく作業を進める工夫をしています。
端材の有効利用
クサビ・ダホなどは極力端材から取り、杉・檜は家具の扉などに利用できます。
細かな部材を使う為に端材は殆ど出しません。

