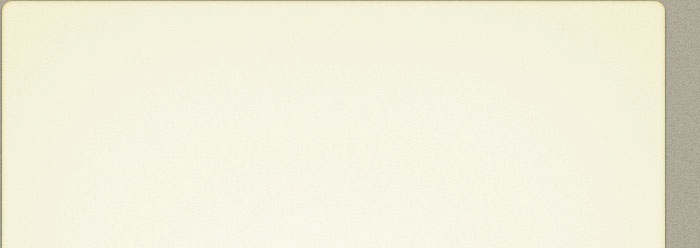現在、一般に建てられている木造建築のほとんどが在来工法です。
これからご紹介する建物は、日本古来の伝統文化である木造建築の良さを活かし、さらに改良し、構造・意匠面などを考え、現代の住まい方に合わせた建築にしております。
なぜ、伝統構法なのか。
現在の在来工法は金物に頼り、本来の木造建築の特徴である木組みの重要性を失ってしまいました。
木材は常に収縮を繰り返す為、建て方の時にいくら金物を強固に締めても、時が経つにつれ緩みが生じてしまうという難点がありあます。
在来工法のもう一つの特徴は、筋交いを多様する点です。
筋交い・土台・桁の交点に水平荷重がかかると、力が一点に集中してしまい、欠損の大きな原因になってしまいます。
この交点へも金物が使われています。
金物の耐用年数が建物の寿命となってしまうという点も危惧される点です。
新伝統構法では、筋交いは使わずに足固め・桁固め・通し貫で水平荷重の力に抵抗しています。桁にかかる水平力を足固め・桁固めで柱を拘束し、通し抜きを通して力を柱に均等に分散します。
金物の代わりにダホや込み栓、割り楔を使うことで、金物は一切使わずに十分な強度を得られます。
もう一つの特徴は、伝統構法では框や差し鴨居などに大きな材を使用していましたが、現代では大きな材を事前に乾燥し準備する事が困難な為、人工林の120㎜角材を重ね合わせる事で大梁の要素を果たせるという点です。
同一材を使う事で事前に乾燥する事ができ、さまざまな住宅への対応が可能となります。
森林の活性化の為に、最低でも100年は壊されない建物を建てること。
そして、100年後に再生ができる建物を建てること。
先人から受け継がれる伝統構法から学び、現代へ生かす建物を新伝統構法は期待されています。